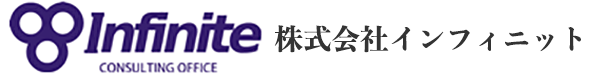自分の原点と『ハイキュー!!』との出会い
「ハイキュー‼」は、バレーボール好きのみならず、内容もキャラクターも魅力的で何度見ても新たな気づきを与えてくれる作品だ。
自分は中学と高校でバレーボールをやってきた。例に漏れずどこにでもいるような選手だった。背が高いわけでも、特に秀でた技術やパワーがあるわけでもない。試合で目立った活躍をした記憶もない。いわば「普通の部員」だった。
社会人になり、組織作りを支援するコンサルタントとして活動する中で、『ハイキュー‼』に出会い、家族に呆れられながらも何度も何度もアニメを見返してきた。
最初に心に刺さったのが、ファーストシーズン第4話「頂の景色」だった。
影山が言う。
「スパイカーの前の壁を切り開く、そのためのセッターだ」
日向が言う。
「自分一人では見ることのできない頂の景色」。
この2つの言葉は、ただのセリフではない。『ハイキュー‼』全体を貫く大きなテーマだ。
影山の言葉には、セッターとして仲間のために道を切り開くというポリシー(価値観)があり、日向の言葉には、チームでしか見られない未来へのビジョンがある。
そしてその両方が、彼らの“ミッション(使命)”を形つくっている。
組織を前に進めるためには、こうした個人のポリシーやミッション、そして組織のビジョンが必要だ。
勝つために、成果を上げるために、数字だけでなく、「自分が何を目指したいのか」「仲間と何を実現したいのか」という言葉が、組織の力になる。
日本の男子バレーボールと烏野高校
日本の男子バレーは、かつて1972年のミュンヘンオリンピックで金メダルに輝いた歴史がある。
まだ、小学校の低学年だったがテレビの前で手に汗を握っていたことを覚えている。「ミュンヘンへの道」というアニメが毎週テレビで放送され、当時の松平監督や12人の選手がそれぞれ取り上げられ、バレーボールが身近な存在となった。
しかし、日本の男子バレーは長い低迷期に入った。それはかつての烏野高校と重なる。
「もう日本の男子バレーが世界のトップになるなんてないだろう」と、悔しさと諦めが入り混じる中、次第に関心も薄れていった。久しぶりにみた観た東京オリンピックは準々決勝で敗退。
それでも、2023年のネーションズリーグで銅メダルを獲得したというニュースには驚いた。国際大会で約半世紀ぶりの快挙。
「なぜ男子バレーは強くなったのか?」と知りたくなった。そんな時友人が「今の日本男子バレーのチームは『リアルハイキュー!!』だよ」と教えてくれたのをきっかけにサブスクで『ハイキュー!!』を見始めた。
偉そうにコラムを書いているが、実はここ2~3年で見始めたばかりの、まだまだ新米の『ハイキュー!!』ファンだ。
『ハイキュー!!』は、ただのスポーツアニメではない。
弱くても、背が低くても、パワーがなくても、チームは強くなれる。
烏野高校の歩みは、日本男子バレーの歴史とも重なる。
そして自分のように「何も出来なかった選手」には、傷口に塩を塗られたような後悔と苦い想いを呼び覚ます。
ただ、この想いこそが、 「組織に、他者に貢献したいという」今の仕事の原点につながっているのだと気づかされた。
このコラムでは、そんな『ハイキュー!!』のエピソードをもとに、組織やチームの在り方を考えていきたい。
アニメの内容を解説するつもりない。
自分自身の体験や感情を交えながら、リアルな視点で語っていく。
「チームって、こうやって強くなるんだ」ということを。
組織づくりに悩む人、チームでの役割に迷う人に、少しでもヒントとして届けたい。