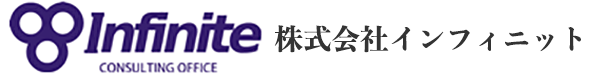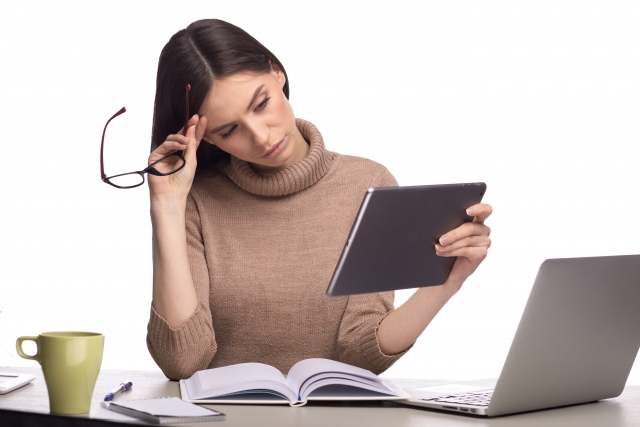クレームがなかなか減らない、不良品の発生が年々多くなってきている 等、良くない状況が続いていいる中小企業の経営者の皆さんと考えていきます。
原因の特定はどこまでやっていますか?
以前このような会社がありました。製造業の会社で、不良品を前年度から2割削減の目標を毎年掲げているにも関わらず数年間は、前年度の実績から1割~2割程度増加している、という一体どうなっているのかというケースでした。
不良品に関する書類やヒヤリングから次の事がわかってきました。
① 社内で発生した不良品及び社外で発生したクレームについては、発生した工程の担当者が報告書を作成して提出されており、台帳で進捗管理ができるようになっていた。
② 原因の特定及び是正処置は、発生した工程と品管のセクションが関わりながら進めていた。
③ その結果は、毎週の会議で経営層に報告されていた。
上記の取り組みは、いたって当たり前のことであり、仕組み上からみて問題が無いように見えます。でも、これらの不良品の報告書の原因の欄には同じことが何枚も書かれていました。
そこで、現場の作業者にどんな状況の時にミスが起きやすいのかを中心に確認したところ、図面の寸法の数値がつぶれてしまい見づらくなっている時や、加工範囲がわかりにくいときに、上司や関係者に確認をしないまま加工してしまうことで不良品が発生してしまうことがわかってきました。
これを読まれている皆さんは、なんで確認しないのかと思うはずです。自分もそうでした。
納期が押し迫ってしまい焦りが出た時や、何とかなるだろうとそのまま作業を進めていること等も確認されました。こんなことがのことが見過ごされているのかと驚いた事と、同時によくありがちな話でもあると感じました。非常に矛盾していますが。
報告書にある発生原因の内容も、「図面の確認不足」や「上司への確認をしなかったこと」等が書かれていました。
その会社では、上司を含めてそれ以上何が原因なのかについて話し合わず、報告書を書くのが当たり前になっていました。再発防止より報告書を作成するのが目的化していました。
それにしても原因の追究が浅すぎて、とても真の原因にたどり着ける状態ではありませんでした 。
なぜ、再発するのか
はたからみると、複数の部門の担当者が集まって検討し、対策についての進捗を管理するための体制、クレームやミスを一覧にまとめた台帳の整備、や会議体での進捗の確認の実施等、再発防止に必要な事が整っているように見えました。
それでも、なぜ同じ事が何度も起きているのでしょうか?次のことが考えられます。
① 担当者が、原因の調査について関係者を巻き込んでなく、自身の今までの経験や視点だけで実施し、その結果状況報告に留まった内容となり、真の原因の特定に至らずに報告書を作成してしまい、それを責任者が認めてしまっていること。(担当者に丸投げの状態)
② 現場に作業者と品管部門が慣れ合いの状況下にあり、目の前に起きた事だけに着目してしまい、それ以外の事を調べることをしなくなっていること。:あきらめの状態に陥っている。(担当者に自覚はない)
③ 規定した手順通りに対策を文書化してまとめたことで、有効性の評価まで意識がいかずに組織全体が満足した状態になってしまっていること。
④ 原因の特定より、責任だけ追及されてしまい、罰則だけ適用されてしまうので、関係者が協力的でないこと。
思い当ることはありませんか?
⑤もう一つあります。経営層の関与が薄い会社です。会議体を始めとする発信の場で、品質に関するコメントが殆ど確認できるないケースがあることです。
これは、トップが品質に関する関心が薄い場合は、現場にもその認識が無意識に広がり、品質の重要性の意識が低下します。トップが常に品質の重要性について発信し続けていることは、品質の向上に不可欠です
根本原因を明確にするために、効果的な9つのこと
再発させないためにどうしたらいいのでしょうか。 これらのことが一番知りたいと思います。
まず、原因の調査について次の事を行っていきます。
① どこで:どの工程で、どの作業場所で 起きているのか
② どのような時に起きるのか:例 納期に迫られて、新規の製品に取り掛かってしまった、図面の寸法が見にくく、そのまま作業を続けたため
③ 誰がよく起こしているのか:経験の浅い社員か、スキルが低い社員か、傾向をみる
④ どのような作業をしている場合に起きているのか
⑤ マニュアルや手順書はあるのか、その内容は最新の手順が網羅されているか
⑥ 関連する作業について、どのような教育訓練は実施され、担当者が理解されているのを確認できているのか
⑦ 作業方法、材料、作業者、設備・機械、製品 等について変更点はなかったか
⑧ 不良品が発生した際のデータを活用しているか
⑨ 発生した作業に関わっている(直接、間接 問わず)全ての人たちによって調査が行われているのか
どうか、これらのことを踏まえて、相手に答えやすい質問をして、具体的な回答を引き出すことをやって下さい。
発生させた担当者を責めたり、注意をしただけで再発を防ぐのはさすがに難しいです。担当者が責任を追及されるだけでは、自分に不都合なことを話さず、正確な情報も提供されません。
この事は、担当者を責めるのではなく、組織として再発を防ぐためにどのように取り組まなければいけないのかをはっきりさせることが目的であること。そして一緒に協力して原因を究明し、よりよい作業環境を作っていくという事を担当者にしっかり説明して下さい。
そのためにも、担当者に心理的な安全・安心の場を作っていくことが原因の究明に最も必要です 。どのようにしたらそのような場が出来るか次の機会にお話しをします。